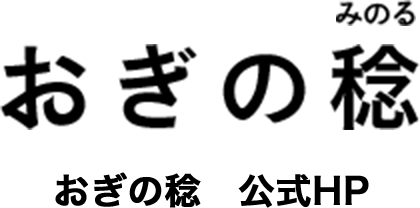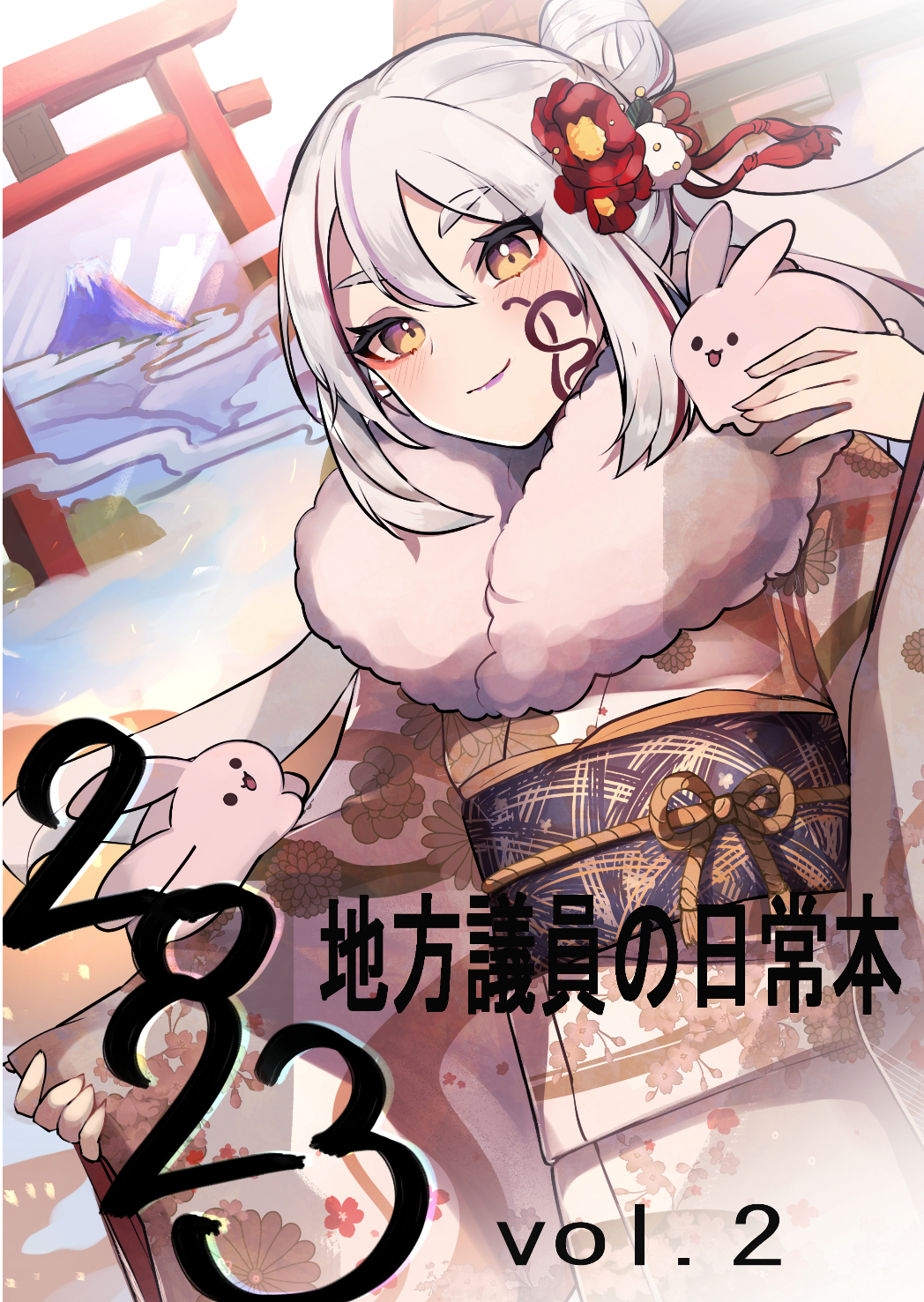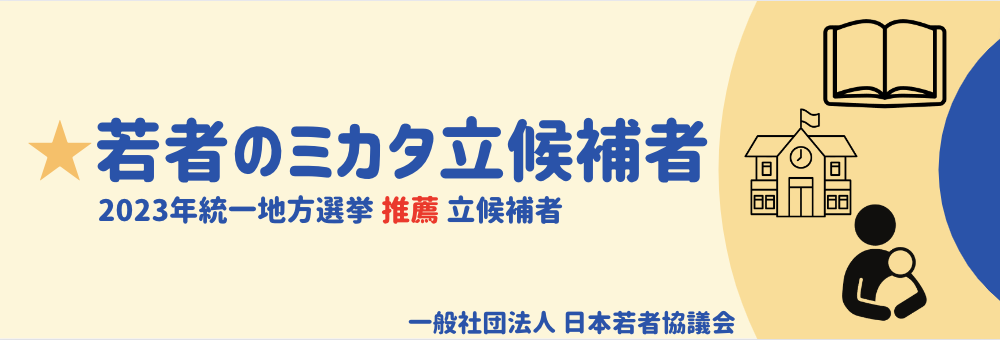大田区議会予算特別委員会で質問しました!
大田区議会議員のおぎの稔です。今回は会派を代表して令和7年の大田区議会の予算案について総括質疑を行わせていただきました。テーマは事務事業評価について、福祉について、キャッシュレス決済について、羽田空港(空港公園)について、国際都市についてです。 答弁などは録画中継もおって議会の公式HPで公開されます。また、質問の感想などもいただけますと幸いです。
① <事務事業評価について>
つばさ大田区議団のおぎの稔です。今回は会派を代表して令和7年度大田区一般会計予算に対する総括質疑を行わせていただきます。理事者の皆様におかれましては、簡潔明瞭な答弁をよろしくお願いいたします。 本年1月20日からアメリカではドナルド・トランプ大統領の2期目の任期が始まりました。就任して1週間で三十を超える大統領令に署名し、破壊的とも言える政策転換、新たな政策を実行しています。アメリカファーストを掲げて民意を得て突き進むトランプ大統領を見ると、私は2020年1月に欧州議会でイギリスのEU離脱が決まった際にイギリス代表のファラージ氏のした 「これは世界主義(グローバリズム)と大衆主義(ポピリズム)の戦いだ。君たちは大衆主義を毛嫌いしているかもしれないが、おかしな話をしよう、大衆主義はすごく人気が高まっている。」演説を思い出します。5年前のこの演説はその後に起きることを予言するかのように、世界情勢が更に変化していったのは皆様もご存知の通りです。
国際協調なのか、自国ファーストなのか。今までの国際社会の常識、定石が変わろうとしている中、日本、そして大田区もどのように今後の自治体運営を行っていくのかが重要になってきます。
さて、鈴木あきまさ区長が「未来へ加速 新時代の幕開け、住みたいまちNo.1へ」とメッセージを込めた令和7年度の大田区の予算は3527億958万円余となっております。今回の予算案の編成は、「心やすらぎ 豊かさと成長を実感できる 新しい次代に向け 力強く踏み出す予算」と方針を位置づけ編成されていると聞いております。 過去最高を毎年更新する本区の予算の中で、それをどのように適切に執行していくのか、最小の力で最大の成果を発揮するためにどうしていくのかが問われていきます。行政の行う事業の中では時代に不要となったもの、民間にアウトソーシングできるものなどもあります。そうしたものも放置しておけば、行政は肥大化し、限られた予算をうまく活用できないことにもなっていきます。では、どういう事をおこなえば、行政の肥大化を防ぎ、適切に執行されているかを判断できるのか。その為の手法が事務事業評価の公開であります。 事務事業評価の公開については、わたくしも前回の大田区議会議員選挙から訴えてきました。鈴木あきまさ区長が事務事業評価の公開について行っていく旨の答弁をいただいたこと、大変うれしく思っております。また、その公開の時期についても昨年の定例会にて令和7年度に行われる事業、まさに今回の予算案にある基本計画に関係のする事業を、令和8年度来年度に公開をしていると伺いました。事務事業評価の基準について、どのような基準を持って評価をしていくのかも大切となります。 事務事業評価の公開については「自治体が実施している事務事業について、予算の執行率や進捗度という観点からだけでなく、社会的 要請や区民ニーズによる必要性、事務事業の目的に対する成果、最も合理的で経済的な手法により 実施しているかといった効率性の観点から評価を行い、その結果を行政運営の改善や見直しに反映することにより、最小の経費で最大の効果を挙げる行政運営の実現を目指していく」と定義し、公表している自治体もあります。事務事業の評価について、大田区は誰がどのような基準をもとに成果指標を作成していくのでしょうか。回答をお願いします。①
②
続けて事務事業評価について更に伺います。事務事業評価に合わせて、基本計画の内容に沿っていないであろう常時行われる業務や職員の負担も存在します。 コロナ禍を契機に、本区の職員もメンタルを理由とした休職が増加するなど、問題となっておりました。口に出さないけど負担を受けている職員がいる。そう言う声を拾うことができなければなりません。声なき声に応える仕組み、評価も必要です。 多層多難に区民から行政ニーズが求められる変化の激しい昨今、短期間で色々なものが変わる。それに対応しなければならない職員は頑張っていると考えます。令和7年4月1日からは東京都では東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が施行されました。カスハラは許されないことです。さまざまな課題中で矢面に立たされている職員がいることもこの目で見てきましたが、これを機に現場の状況が改善することも願っております。出張所や一階の窓口で怒鳴り込んでいる区民の対応をしている職員さんもいますし、わたくしたち議会のことであれば議会事務局など職員はよくやってるくれていると思います。今回の予算の概要でも福祉現場におけるハラスメント対策事業などについても予算が計上されておりますが、福祉、教育、人権といった場でもそうはいっても相手側が弱者だからといままでは声を上げづらかった。むしろ、声を上げることで加害者扱いされてしまうような事例もあったやもしれません。 質問します。成果主義、指標では評価されない仕事をする職員もいると思います。こうした職員の仕事の評価、またフォローについてどのようなことを考えておりますか?見解を伺います。②
<福祉について>
③ 続きまして、福祉について伺います。今回の予算案では障がい者向けグループホームの整備促進について5000万円の予算が計上されております。これは、ここ数年、課題となっていた多摩川2丁目のグループホーム施設も関連しての予算と聞いております。こちらの施設については、この議場にいる多くの方が指摘をしており、自分も議会で訴えてきたことです。入居者について一度、公募を開始したものの、その後申し込んでいたまま止まってしまったことについても大変残念に思うこと、この場でも訴えてきました。 今回の予算増加はグループホームの建設について、補助金の上限が今までの2000万円から3000万円に上昇したことでそのための予算計上になったと聞いております。こうしたことでどのようなことを期待しますか?③
④ 重度の方のグループホームの建設については、今回もさまざまな苦労の中、今回の予算措置となり、前向きに進むことを期待します。一方で、重度の方の施設設置については今後も、同様の課題を抱えていると考えます。広さの問題、近隣との調整をしなければならない課題、事業者や職員を集めなければならない課題。そして何より最近の物価高上昇にあるような費用の問題。そうした課題が山積しているからか、大田区は重度の方向けのグループホームの施設設置には数字目標を設けていないと聞きます。数値化することが難しいというのも理解しますが、目標がないまま進めることも難しいのではないかと懸念します。先ほど、事務事業評価の公開について質疑しましたが、行政需要を把握し、適切な予算配置をしていくという意味でも、目標は必要ではあります。8050問題が社会問題として語られて久しいのですが、今まで親族のお世話になっていた重度障害の方がこの先、家族という支えて、受け皿を失い、どう生活していけばよいかわからなくなる。そうした事例も今後起きてくると考えます。私に今回、多摩川2丁目の施設について相談してきた方も、重度の方を親族に抱えたご高齢の方でした。そうした時限的な課題を抱えた今後の需要把握、適切な支援の移行も必要となってきます。 質問します。大田区として重度のグループホーム建設についてどのような考えのもとに計画を立て、設置に向けて動いているのでしょうか。見解を伺います。
<キャッシュレスについて>
⑤ 続きましてキャッシュレス決済について伺います。キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン事業として、今回4億5165万円余の予算が計上されております。私はこうしたキャッシュレス化、電子化には賛成の立場です。公共機関、行政サービス、商店街、自治会、様々なことがスマホ一つで完結する。そういったことが進んでいけばより便利で安心した社会になると考えています。外国籍の方や日本語を母国語にしない方にとって、また障害等をお持ちの方にとっても、利便性が高まる面もあるかもしれません。昨年は東京都もキャッシュレスキャンペーンを実施していました。ひとえに電子化、キャッシュレスといっても様々な考え方もあるでしょう。冒頭に質問をした事務事業評価の公開のように、どういう目的で、どういう効果を得たのか、手法は適切だったのかが行政の行う事業に求められます。今回の事業は区民限定ではなく、区内であればだれでも使える形となっております。 では、質問します。今回のキャッシュレス決済導入は、本区はどのような目的、また効果を見込んだもとに導入をされますか。見解をお示しください。➄
⑥ 今回の「キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン」の予算を見ていますと、今年の秋頃を目途に、還元率20%、期間中の付与上限は5,000ポイントで実施を予定しています。とあります。還元率については他自治体などでは30%で実施しているところもあります。こうした還元率やポイントの内容などをどういう視点で設定しているのか、伺います。先ほど、お答えになりました。このキャンペーンを行う目的についてですが、区内の消費喚起をはかり、経済活性化につなげていくということは予算の発表時にも区長がご説明になっていたところです。大田区の消費喚起をはかり、経済を活性化していくのにはどのくらいの規模、また内容のキャンペーンが良いのかも大切な視点です。 使用者へのポイント還元等は目的に対して予算の額は効果は正しいのでしょうか?区が期待する効果について教えてください。⑥
<羽田空港について>
⑦続きまして、羽田空港について伺います。 世界の中で羽田空港は5位の利用者を誇る巨大な国際空港です。2024年10月には国際線の利用客数が過去最高となる204.9万人。また国内線国際線を合わせると2024年10月は791万1758人とこちらも同様に1000年を上回る数字を記録しました。 成田と羽田の2つの首都圏空港の能力が限界に達しつつあり、政府が2030年に目指す訪日客6000万人の達成を考えると更に空港の能力を強化する必要もあります。今年に入り1月の訪日客数は378万1200人となり過去最高を記録しております。こうしたインバウンド需要、訪日外国人が増加していく中で空港隣接都市である本区はその需要、経済効果をどうやって確保していくか。こぼさずに回収していくか。その視点も大切となるため、質問させていただきます。 まずは第一ゾーン、空港公園について伺います。先日の代表質問でも公明党の田島委員も触れておりました。 羽田空港公演の第一ゾーンについて、都市公園の事業予定者が決定しました。決定した事業者の提案については、本区は「「羽田みらいパークマネジメント」の提案は、本事業の公募設置等指針や要求水準書等に示した要件を満たしたうえで、本公園を含む羽田空港跡地第1ゾーン全体及び周辺資源との連携や、公園の魅力を高める公募対象公園施設が提案されており、区内に限らず広く親しまれる公園となることが期待されるなど、地域に密着し立地特性を捉えた提案が特に高く評価されたものである。」と評価しております。私としても今までこの議場でも訴えてきたように、都市公園であることも必要ですが、羽田空港内のこの立地をただの公園とするのではなく、民間の商業施設や遊戯施設などを入れて運営することを賛成していたので区の評価についても賛同をさせていただきます。羽田空港を活用できる最高の一等地でもあると考えられるこの土地、今回提出されたイメージ図を見ると民間施設なども有し、立地と民間の力を上手く活かせる素晴らしい提案であると考えます。私は特に、イノベーションシティに面した側、大屋根や芝生広場、はらっぱの部分も活用し、民間の力を呼び込み、羽田が国内外から大きく注目されるような野外イベントなどもできるような形での整備を行得るのではないかと期待しております。 質問します。この事業はイノベーションシティとの連携や民間との連携について、大田区のランドマークになれるくらいの大きな可能性を秘めているのではないかと考えますが、この都市公園にどういったことを期待するか区の見解を伺います。 ⑦
⑧続いて、空港の周辺のまちづくりについて伺います。昨年の本会議でも質問させていただきましたが、この羽田空港第一ゾーンには、多摩川に面した護岸。国有地があります。また、海老取り側周辺や中央防波堤などを含めて空港周辺は大きな可能性を秘めていると考えます。私が残念に思うのは、東京都が出している東京ベイ eSG まちづくり戦略 2022についてです。この計画、昭和島、京浜島、平和島、中央防波堤といった羽田空港の北部が一部入っていますが空港に隣接する西側付近、羽田の街やその周辺がスルーされております。 羽田空港の西側や今回の空港の第一ゾーンのイノベーションシティ。今後作られる都市計画公園周辺などもこの計画の中に入り、空港周辺の開発が東京都の大きな活力になっていくといった計画も必要なのではないかと思います。 質問します。大田区が目指す空港臨海部のまちづくりの実現に向けて、どのように取り組んでいくのか考えをお伺いします。⑧
<国際都市について>
⑨さて、インバウンド、観光や産業といった面から羽田空港について伺わせていただきました。続いて、生活という面から国際都市について伺います。外国人住民との摩擦、トラブルがインターネットやメディアなどで取り上げられることが多くなりました。ゴミ出しなどの生活トラブルから、犯罪、暴力行為など社会問題まで様々です。私は排外的な主張や外国人差別に同調するつもりはありません。しかしながら、言葉の違いや文化の違い、価値観の違いなどからトラブルが起きていること。日本人と比べて多いわけではありませんが外国籍の方も含めた犯罪行為などが行われていることも事実であり、社会全体でその対策を考えていかなければなりません。 少子高齢化社会の中で、外国人の労働者の皆様の力を借りることは大切です。これは労働だけでなく、地域社会の維持という面でもそうなるでしょう。労働者として日本に来て生活をする中では彼らを地域住民として、区民として考え、福祉や教育なども整備していく必要があります。今までも本区はおおた国際交流センターなどを中心に多文化交流、共生社会施策を行ってきました。外国人というのは、特別な存在ではありません。しかしながら国際都市、多文化共生という政策が、地域や福祉という概念から独立した概念、政策のように受け取られてしまっているのではないかと私は危惧しています。今後も本区の外国人住民は増え、その子供、孫といった世代の方も増えていきます。否応なしに外国籍の方も地域住民であることを前提とした施策、まちづくりが必要となります。 質問します。国際都市としての政策の進展や外国人住民の増加に伴い、「国際都市」という概念が、どこか遠い存在から区民にとって身近なものとなり、地域における外国人との共生への取り組みが一層重要性を増してきていると考えます。本区の地域における外国人支援、多文化共生推進についての区の考え伺います。
⑩区内の生活者としての外国人が増加する中、特に日本語を話せず社会に溶け込めないような外国人が孤立することなく、暮らしやすい環境を整えていく必要があります。そうした外国人住民の孤立、孤独が暴力や犯罪行為などに走らせる要因になるのではないかと懸念を持っております。様々な行政の文書、標識、サインなども更新をしていく必要がありますし、今回はグループホームで福祉に触れましたが、誰かを追い出す、特定の人を優遇や排除するのではなく、簡単でわかりやすいデザインに変えていくことは、今後複雑化する社会では求められていくでしょう。 コミュニケーションに自信がなく社会との接点に乏しく、家庭にとどまっているような方などへの支援が必要と考えますが、外国人区民が地域で暮らしやすくなるような支援について、区の取り組みを伺います。⑩